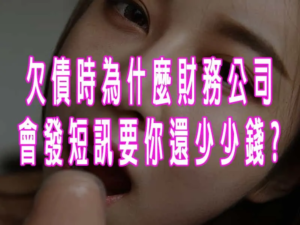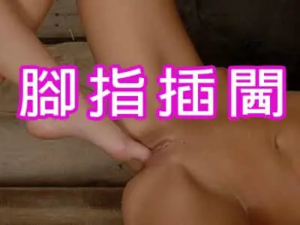売春をなぜ「売春婦を呼ぶ」というのでしょうか?起源探究と文化分析

目次

「鶏を呼ぶ」の文字通りの意味と意味論
文字通り、「鶏」の「鶏」は中国語では通常家禽を指しますが、俗語では「鶏」は性労働者、特に女性の性労働者を指します。
広東語では、「チキン」は性労働者、特に女性の性労働者を指すのによく使われます。この言葉は、性労働者に対する初期の軽蔑的または婉曲的な用語に由来する可能性がある。これは、女性を指して使われた英語の「bird」や「chick」という言葉に似ており、後に特定の意味を持つようになった。
昔、一部の地域の売春宿は「チキンハウス」と呼ばれていました。性労働者が比喩的に「ニワトリ」と呼ばれていたからです。したがって、サービスを求めて売春宿に行くことは「鶏を呼ぶ」と呼ばれ、それは「鶏」を見つけるために「鶏小屋」に行くことを意味します。
「喚」は呼び出す、呼びかけるという意味で、「喚起」と合わせて風俗嬢を誘うという意味もある。しかし、この単語の形成は単純な文字の組み合わせではなく、歴史、文化、言語の進化と密接に関係しています。
「鶏を呼ぶ」とは文字通り「鶏を呼ぶ」という意味で、これは売春婦を探したり呼び出したりするという意味にまで広がり、売春を勧誘する行為を表しています。

歴史的起源と言葉の進化
「焦酌」という用語の起源については正確な文献記録は残っていないが、歴史的背景からその形成過程を推測することはできる。古代中国では、性産業は古くから存在していたものの、その名称は「売春宿」「売春婦」「娼婦」など、より曖昧な形で表現されることが多かった。現代社会の変化、特に都市化と商業化の発展に伴い、一部の地域では性産業が徐々に公然と行われるようになり、この現象を表現する新しい俗語が言語の中にも生まれています。
性労働者の同義語としての「チキン」は、広東文化とより深いつながりがあるのかもしれません。香港や広東省では、「チキン」は昔から性労働者を指す言葉として使われてきましたが、これは地元の方言や文化的背景に関係しているのかもしれません。たとえば、広東語では、「鶏」は動物の名前であるだけでなく、下品なものや軽薄なものを表すときにもよく使われます。この用法は 20 世紀初頭に香港で徐々に普及し、広東語文化の広がりとともに他の中国語圏にも影響を与えました。
「売春婦を呼ぶ」という具体的な用語については、現代の都市生活における性取引の商業化に関係している可能性があります。香港などの歓楽街では、客が性労働者と連絡を取る際、通常は電話による呼び出しや仲介業者による手配といった特定の手段が用いられる。この「召喚」という行為は簡略化されて「呼ぶ」となり、性労働者は「チキン」と呼ばれるため、「チキンを呼ぶ」という簡潔で生き生きとした言葉になった。

文化的および社会的文脈
「売春を呼ぶ」という言葉の流行は、その背後にある社会的、文化的背景と切り離せないものです。まず、性産業は中国社会において長い間、道徳と法律のグレーゾーンにあり、そのため関連語には曖昧な意味合いや軽蔑的な意味合いが込められていることが多い。俗語として、「売春婦を呼ぶ」は、「売春婦」などのより直接的な言葉の直接的な使用を避け、同時に、ユーモラスまたは軽薄な言葉によってその行為の道徳的論争を軽視します。この言語戦略は、ある程度、性産業に対する社会の矛盾した態度を反映しています。つまり、需要がある一方で、言語を通してその繊細さを覆い隠そうとする試みもあるのです。
第二に、「売春婦を呼ぶ」ことの流行も、都市文化の発展と密接に関係している。香港やマカオなどの商業化が進んだ地域では、20 世紀中盤から後半にかけて性産業が徐々に比較的成熟した市場を形成していった。電話やインターネットなど現代の通信ツールの普及により、性労働者を呼ぶ方法はより便利になった。 「売春婦を呼ぶ」という言葉の出現は、この迅速で便利な取引モデルにぴったりと適合し、わかりやすい表現となった。
さらに、広東文化の影響も無視できません。中華世界の文化の中心地の一つとして、香港の言語と俗語は他の地域に大きな影響を与えてきました。 「叫鸡」という言葉は香港から他の中国語圏に広がり、広東語以外の地域でも広く使われており、文化交流における言語の強い活力を示しています。

言語における比喩と象徴
言語学では、「売春婦を呼ぶ」というのは比喩的な表現です。性労働者を「売春婦」と比較することで、言葉は単純化されるが、同時にある種の軽蔑的な意味合いも持つことになる。この比喩は単独で存在するわけではなく、他の言語でも同様の現象が見られます。たとえば、英語の「chick」という単語は、軽薄な意味合いを伴って若い女性を指すために使用されることがあります。フランス語にも、動物を使って比喩的に性労働者を表す同様の俗語があります。この異文化言語現象は、人間は繊細な話題を説明するときに、道徳的または社会的タブーに直接触れることを避けるために、比喩や間接的な方法を使用する傾向があることを示唆しています。
しかし、「売春婦を呼ぶ」という表現は、論争も巻き起こしている。この用語は性労働者に対する言語的な蔑称であり、この集団に対する汚名を強めるものだと考える人もいる。近年、男女平等や人権意識の高まりに伴い、一部の社会運動では、性労働者を表現するのに「売春婦」や「女」ではなく「セックスワーカー」といった、より中立的または敬意を表す言葉の使用を求める動きが出始めている。この変化は言語と社会的価値観の相互影響を反映しています。

チキン・コーリングの結末
俗語として、「売春婦を呼ぶ」ことは表面的には単純に思えるかもしれませんが、実際には豊かな歴史的、文化的、言語的意味合いを含んでいます。その起源は広東文化、都市化、性産業の商業化と密接に関係している可能性があり、その人気は性的な話題に対する中国社会の複雑な態度を反映している。言語学的に見ると、「売春婦を呼ぶ」というのは、動物のイメージを通して繊細なテーマを簡略化した典型的な比喩表現であり、ある種の軽蔑的な意味合いも持っています。
社会の進歩と概念の変化に伴い、「風俗嬢を呼ぶ」などの言葉の将来は課題に直面するかもしれません。言語は文化の担い手として、社会の現実を反映するだけでなく、人々の価値観にも影響を与えます。 「売春婦を呼ぶ」という言葉について議論する際には、その言葉の背後にある社会構造や権力関係についても考察し、より包括的かつ敬意ある態度で関連する現象を見るべきです。結局のところ、「鶏を呼ぶ」ことの起源と意味を理解することは、言語の探求であるだけでなく、文化と歴史についての深い考察でもあります。
さらに読む: